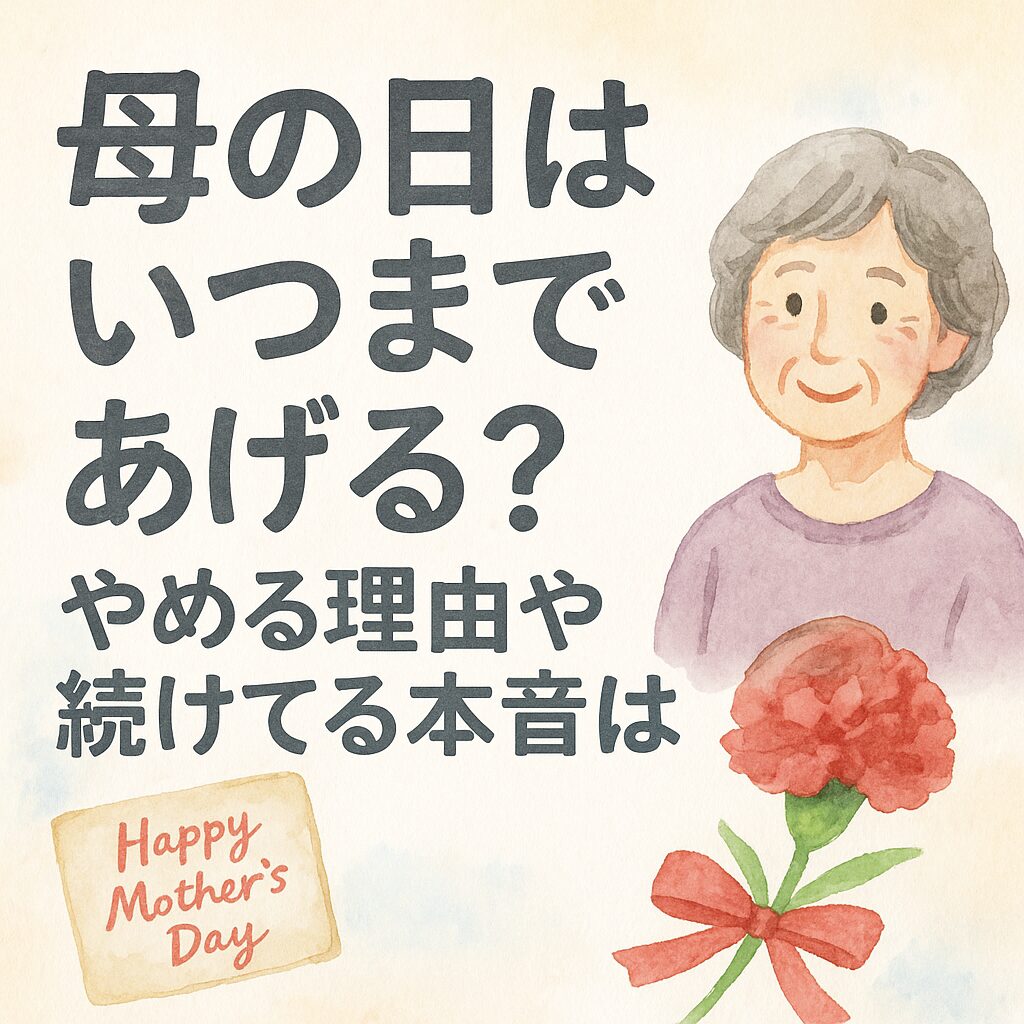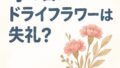「母の日、そろそろやめてもいいのかな…?」
ふとそんな風に思ったことはありませんか?
毎年の恒例行事になっている人もいれば、なんとなくモヤモヤを感じている人もいると思います。
この記事では、「母の日はいつまであげるべきなのか?」という素朴な疑問を軸に、あげ続けている人、やめた人、それぞれの本音や背景を深掘りしてみました。
自分の中の正解を見つけたい人に、ぜひ読んでもらいたい内容です。
母の日はいつまであげるべきか迷ったときの考え方
母の日って、何歳まで贈るべき?
結婚したら?義母には?
そんな「いつまで?」問題に、みんながどう考えているのか、実際の声も交えながら見ていきますね。
年齢による線引きはある?
「何歳まで母の日にプレゼントってあげるもの?」と迷う方、意外と多いんです。
特に30代・40代になってくると、自分も“親”になる立場だったりして、母の日の意味合いが変わってきますよね。
でも実際のところ、「〇歳まで」みたいな明確なラインはないんですよ。
プレゼントを贈るかどうかって、年齢よりも“気持ち”と“関係性”による部分が大きいんです。
例えば、70代や80代の母親でも、毎年子どもからの気遣いを楽しみにしている方もいますし、逆に「もう気を遣わなくていいよ」と言うお母さんもいます。
なので、“何歳になったからやめる”というより、“お互いにどう思っているか”を基準に考えるのが自然かなと思います。
結婚後も渡すべき?
結婚した後って、贈り物の範囲が広がるから、正直ちょっと悩みますよね。
自分の母親だけじゃなくて、義母の存在も出てくるから、「どっちにも渡す?」「パートナーはどう思ってる?」と気を遣う場面が増えます。
でも基本的には、結婚しても“感謝の気持ち”があるなら、渡してOKです。
特に結婚直後の頃は、義母との関係をスムーズにするきっかけにもなるので、プレゼントは「挨拶代わり」になることもあります。
ただし、パートナーと価値観がズレてるとトラブルの元になることもあるので、「今年どうする?」って事前に話し合っておくのがベストですね。
義母にはいつまで?
義母への母の日、これは本当に悩ましいテーマです。
初めのうちは「嫁としてきちんとしないと…」と気を張って、プレゼントを用意する人が多いです。
でも、毎年続けるうちに「これは義務なのか?」と疲れてしまうことも。
一般的には、“義母が健在で、関係が悪くない限り”は、ある程度の年数は贈るのがマナーとして好まれます。
ただし、義母側が遠慮したり、「気を使わなくていい」と言ってきた場合は、やめるタイミングでもあります。
感謝の形って、物にしなくても伝わるので、たとえば手紙や電話でも充分ですよ。
あげるのをやめた理由とは
母の日のプレゼントを“やめた”という人も、少なくありません。
その理由としてよく聞くのが「母が欲しがらなくなった」「なんとなく疎遠になった」「感謝はしてるけど形式ばるのが苦手」というもの。
実際、母親世代も「物をもらうより気持ちだけで十分」と感じてる人は多いです。
また、距離があったり、関係性にストレスを感じている人にとっては、「贈ること自体がしんどい」ということもあるでしょう。
そんなときは、「母の日=プレゼント」という固定観念を手放してもいいと思います。
渡すタイミングが気まずいとき
気まずくなるケース、ありますよね。
「久しぶりに連絡するけど、プレゼントだけ渡すのもな…」とか、「他の兄弟は何もしてないのに、自分だけ送るの変かな」とか。
でも、母の日は“絶好の口実”にもなります。
気まずい関係でも、「母の日だからね」と言えば、案外すんなり受け取ってくれるものです。
それでも抵抗があるなら、まずはLINEやメッセージでひとこと感謝を伝えるのもあり。
そこから少しずつ、関係を戻していくきっかけになるかもしれません。
母の日をやめる人が増えている理由4つ
最近は「もう母の日やめちゃった」という人も増えています。
それって冷たいことなの?それとも自然な流れ?
この章では、やめる人たちがどんな理由でそう決めたのか、そのリアルな事情を掘り下げます。
気を使うのがしんどい
母の日のプレゼントって、毎年選ぶのが地味に大変なんですよね。
何を贈れば喜ばれるか悩むし、「去年と同じだとまずいかな?」とか、「義母にだけ渡してると実母はどう思うかな?」とか、いろんな気遣いが重なります。
特に、義母とそこまで深い関係でない場合は、“プレゼントを贈る行為そのもの”がプレッシャーになってしまうことも。
こういう精神的な負担が重なると、「もうやめてしまおうかな」と感じるのも無理はありません。
やめたからといって感謝がゼロになるわけではなく、むしろ「ストレスが減って気持ちが軽くなった」と話す人も多いです。
母親の反応が微妙
せっかく心を込めて贈ったのに、「あぁ、ありがとう…」と、あまり嬉しそうじゃない反応をされると、正直がっかりしますよね。
なかには、「またこれか」とか「こういうの使わないのよね」と言われてしまった経験がある人も。
母親としては悪気はないのかもしれませんが、贈る側からすればかなり萎えてしまいます。
その繰り返しで、「もう渡さなくてもいいかな…」という気持ちになってしまうのは自然な流れです。
プレゼントが義務感になった時点で、お互いにとって意味が薄れてしまうかもしれませんね。
自分の家庭を優先したい
年齢が上がるにつれて、今度は“自分が母親”になることも増えてきます。
そうなると、「母の日=自分が祝ってもらう日」でもあるし、家庭内のイベントとして忙しくなるんですよね。
子どもの行事が重なったり、家族での予定が増えたりすると、「実母や義母へのプレゼントまで気が回らない」というのが本音。
特に小さな子どもがいると、時間も体力も限られてくるので、やれることが限られてしまいます。
そんな中で無理をしてまで母の日を続けるよりは、いったん距離を置く人も増えているようです。
お金や時間の負担が重い
「プレゼントって、地味に出費がかさむ…」
そんな声もよく聞きます。
特に母が2人(実母+義母)いる場合、それぞれに贈ると出費は倍に。
しかも、ただ贈るだけじゃなく、買い物や手配の時間も必要です。
日常の生活に追われている中で、金銭的にも精神的にも負担になるのは事実です。
その結果、「続けられない」「無理しない範囲にしたい」と考えて、母の日をやめる人が増えてきたんですね。
無理なく、できる範囲で気持ちを伝えるスタイルが求められるようになっています。
それでも母の日を続けている人の本音
やめる人がいる一方で、ずっと母の日を大切にしている人たちもいます。
彼らが続ける理由には、素敵な思いが詰まっていました。
プレゼントの意味や、大切にしている気持ちに注目してみましょう。
感謝を伝えるきっかけ
とくに直接「感謝してるよ」なんて、普段はなかなか言いづらいもの。
でも「母の日だから」という名目があると、自然に感謝の気持ちを伝えることができます。
何か特別なことをするわけじゃなくても、ちょっとしたプレゼントやメッセージを送るだけで、お互いの心が温まる瞬間になります。
こうした「年に一度の感謝のタイミング」として、母の日を大事にしている人は案外多いんですよ。
母が喜んでくれるから
一番シンプルで強い理由、それは「母が喜んでくれるから」です。
とくに年齢を重ねた母親にとっては、子どもからの気持ちが本当にうれしいもの。
物より気持ち、とよく言いますが、その「気持ち」が母の日には詰まってるんですよね。
花束ひとつでも、「今年も覚えてくれてた」と思うだけで、心が満たされる方も多いです。
その笑顔を見たくて、毎年欠かさず続けているという声もよく耳にします。
習慣として定着している
子どもの頃からずっと続けてきた母の日が、もはや“習慣”になっている人もいます。
特に実家にいた頃、学校やテレビなどで「母の日にはプレゼントを」って学んで、そのまま自然に続けているパターン。
そういう人にとっては、やめる理由がないんです。
無理して続けているというより、「今年もこの季節が来たな」という感覚で、毎年同じように母に何かを贈っている。
母の日が生活の一部、季節のイベントのような存在になってるんですね。
毎年の行事として大事にしている
誕生日や正月と同じように、“母の日”を年中行事として大切にしている人も多いです。
この時期になると、母の好きなものを思い出したり、一緒に買い物に出かけたりと、特別な時間を過ごすきっかけになるんです。
忙しい毎日で、親と向き合う時間が減ってきたからこそ、こうした行事を通して「つながり」を感じたいという気持ちが強くなります。
一緒に過ごすことが難しい場合でも、メッセージやプレゼントで“気持ちの距離”を縮めることができるんですよね。
これからの母の日は“かたち”にとらわれなくていい
毎年の母の日、なんとなくプレッシャーを感じていませんか?
これからは、もっと自由に、もっと自分らしく「感謝」を伝える時代かもしれません。
形式にとらわれない、新しい母の日のかたちを一緒に考えてみましょう。
渡し方に正解はない
「母の日=お花やプレゼントを贈らないといけない」と思い込んでいる人、多いですよね。
でも実は、どんなかたちでも、母の日は“感謝の気持ち”さえ伝われば、それが正解なんです。
高価なギフトを用意しなくても、簡単な手紙やメッセージ、ちょっとした手作り料理でも十分。むしろ、「自分らしい方法」で伝えた方が、母にとっては心に響くことも多いんです。
母の日の“かたち”は、人それぞれでいい。
形式にとらわれない自由なスタイルで、自分なりの母の日をつくっていきましょう。
気持ちが伝われば十分
一番大切なのは、「ありがとう」の気持ちを母に届けることです。
どんなに立派なプレゼントを用意しても、義務感や惰性で贈っていると、相手にも伝わってしまいます。
逆に、ささやかでも心からの言葉や行動があると、母の心にはしっかり届くんです。
「ありがとう」「元気でいてね」「いつも助かってるよ」——そんな一言が、何よりも嬉しいプレゼントになります。
大げさな演出はいらなくて、気持ちをちゃんと乗せて届けることが、一番の“母の日”なんだと思います。
お互いがラクでいられる方法を
「毎年の母の日、ちょっとプレッシャー…」という声、本当に多いです。
でもそれって、親も子も“義務”のように感じてしまってるからなんですよね。
大事なのは、お互いにストレスを感じずに続けられるスタイルを見つけること。
例えば、年ごとに交互に渡すとか、「今年はメッセージだけね」と決めておくとか。
無理せず、自然体で感謝を伝えられる関係の方が、ずっと心地いいものです。
「こうしなきゃ」と決めつけず、気軽に話し合って、ゆるく続けていくのが一番です。
プレゼント以外の感謝の伝え方
母の日=物を贈る、だけではありません。
一緒に過ごす時間をプレゼントする人もいれば、思い出の写真をアルバムにして贈る人も。
「ありがとう」を言葉で伝えるだけでも、母にとってはかけがえのない贈り物になります。
また、遠方でなかなか会えない場合は、電話やビデオ通話でも十分気持ちは伝わります。
大切なのは、“何を贈るか”よりも、“どう伝えるか”。
プレゼント以外にも、いろんな形の「母の日」があっていいんです。
まとめ
母の日のプレゼント、続けるかどうかに“正解”はありません。
贈り方も、伝え方も、人それぞれでいいんです。
大切なのは、形式よりも“気持ち”。
無理をせず、自分らしい形で「ありがとう」を届けられる母の日になれば、それが一番素敵なことだと思います。
この記事が、少しでもそのヒントになれば嬉しいです。