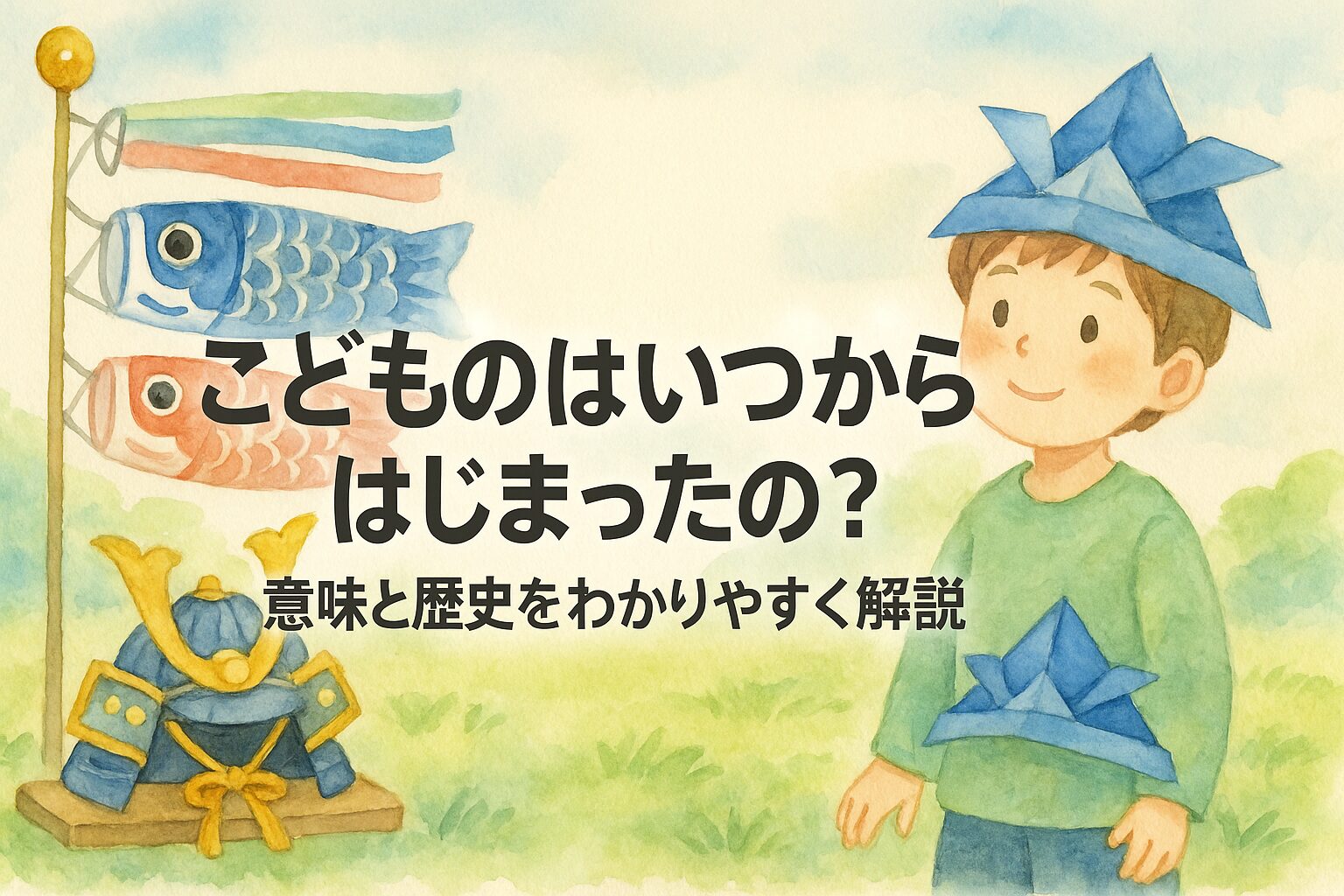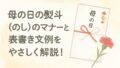「こどもの日って、いつから始まったの?」
5月5日が近づくと、そんな素朴な疑問がふと浮かびますよね。
もともとは「端午の節句」という伝統行事から始まり、やがて戦後に“子どもたちの健やかな成長を祝う日”として、今のこどもの日になっていきました。
この記事では、こどもの日の歴史や由来、なぜ5月5日なのか、そして日本と世界の違いまで、たっぷり解説します!
お子さんに聞かれたときや、家族で話すネタにもぴったりな内容ですよ。
こどもの日はいつから始まった?由来と起源を解説
「こどもの日って、いつからあるんだろう?」そんなふとした疑問に答えるために、こどもの日の起源や、どんな背景で今のような祝日になったのかを詳しく見ていきましょう。
端午の節句が起源
こどもの日のルーツは、なんと中国の「端午の節句」までさかのぼります。
紀元前から続くこの風習は、もともと邪気を払うための行事でした。日本に伝わったのは奈良時代とされ、最初は貴族の間で邪気払いの行事として行われていたんです。
その後、武家社会に入ると、この端午の節句は「男子の健やかな成長と出世を願う日」に形を変えていきました。
鯉のぼりや五月人形などの“男の子らしい”風習も、ここから定着していったんですね。
今でこそ“子どもみんなの祝日”というイメージがありますが、もともとは「男の子のための日」だったことは意外と知られていないかもしれませんね。
明治時代の風習
明治時代に入ると、国の制度がどんどん整えられていき、暦や行事も全国的に統一されていきます。
このとき、端午の節句も正式に「五節句」の一つとして認められ、多くの家庭で男子の成長を祝う日となりました。
特に、武家文化の名残から、鎧兜や武者人形を飾る風習が強く根付きました。これらは「身を守る」や「強く育て」という願いが込められていたんです。
この時代になると、地方ごとの差も減り、“5月5日=端午の節句”として広く知られるようになります。
昭和の家庭にも受け継がれている伝統行事の多くは、この明治期にしっかりと形作られたものなんですよ。
戦後の国民の祝日化
「こどもの日」という名称が登場するのは、実は戦後になってからのことなんです。
1948年(昭和23年)、日本国憲法が施行されたあと、新しい国民の祝日を定めるための法律「祝日法」が作られました。
そのなかで、5月5日は「こどもの人格を重んじ、子どもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日」として制定されました。
この定義を見ると、“子どもだけでなく母への感謝も込められている”という点がポイントですね。
つまり、戦後の日本は“家族みんなで祝う日”として、こどもの日を再定義したとも言えるわけです。
「ただの端午の節句」ではなく、「子どもという存在そのものを讃える日」となったのがこのタイミングです!
子どもの人格を重んじる意味
祝日法で「こどもの人格を重んじる」と書かれたことにも、深い意味があります。
戦前は、どちらかというと「家」や「社会の一員」として子どもを見ていた節がありました。
でも戦後は、個人の権利が大切にされるようになり、子どもも一人の人格として認められるべきという考え方が強まりました。
この背景があって、「こどもの日」という新たな祝日が生まれたんですね。
単なる“子ども向けのイベント”ではなく、“社会全体で子どもの幸せを願おう”という理念が込められた日、というわけです。
現代でもこの理念は息づいていて、保育園や学校でも「一人ひとりを大切にしよう」という教育がされていますよね。
昔は男の子限定だった?
冒頭でも少し触れましたが、こどもの日はもともと“男の子のための日”だったんです。
これは端午の節句が「武士の文化」に深く関わっていたことが影響しています。
鯉のぼりや鎧兜は、武家の「男子に勇ましく育ってほしい」という願いから来ている風習です。
一方、女の子には「ひなまつり(3月3日)」があり、こちらはやさしさや健康を願う行事ですね。
しかし現代では、男女の区別なく「こどもの日」はすべての子どもを祝う日として広まっています。
とはいえ、今も「男の子には鯉のぼり」「女の子には雛人形」と分けて祝っている家庭もあるので、地域や家庭によってスタイルはさまざまですよ。
なぜこどもの日は5月5日なのか?
「そもそも、どうして5月5日なんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?
この日付には、ちゃんとした歴史的・文化的な背景があります。由来を知ると、5月5日がより特別に感じられるかもしれません。
季節の節目だった
昔の日本では、「節句」と呼ばれる季節の節目が非常に大切にされていました。
節句とは、季節の変わり目に邪気を払ったり、健康を祈ったりする日です。1月7日(人日)、3月3日(上巳)、5月5日(端午)、7月7日(七夕)、9月9日(重陽)と、奇数が重なる日が選ばれていました。
その中でも、5月5日はちょうど田植え前の時期で、生命の循環を感じさせる大切なタイミングだったんです。
この季節のリズムに合わせて、健やかな成長を願う行事が行われていたわけですね。
自然の力と人々の暮らしが密接に結びついていた時代ならではの発想です。
武家文化の影響
端午の節句が「男の子の節句」として定着していったのには、武家社会の影響が大きいです。
鎌倉時代から江戸時代にかけて、武士の家では、男児が生まれると「家を守る者」として特に大切にされました。
このため、5月5日には家紋入りの旗や、鎧兜、武者人形を飾る習慣が広まりました。
武士にとっては“立身出世を祈る日”でもあり、強くたくましく育ってほしいという想いが込められていたんですね。
その名残が、現代でも見かける「五月人形」や「鯉のぼり」として残っているわけです。
当時の文化が、今も自然と受け継がれているというのはおもしろいですよね。
菖蒲と勝負の語呂合わせ
5月5日に飾る植物といえば「菖蒲(しょうぶ)」ですが、これにも大切な意味があります。
菖蒲は昔から香りが強く、邪気を払うと信じられていました。だから、軒先に吊るしたり、お風呂に入れたりして使っていたんです。
それだけでなく、菖蒲(しょうぶ)という言葉が「勝負(しょうぶ)」と同じ読みであることから、男の子の強さや勇気を願う象徴にもなりました。
語呂合わせが日本人らしい感性ですよね。
菖蒲湯に入ると、身体の芯から温まって風邪を引きにくくなるとも言われていて、昔の人たちの知恵も詰まっています。
国の制定理由とは
先ほども少し触れましたが、こどもの日が国民の祝日として定められたのは戦後です。
1948年に施行された「国民の祝日に関する法律」によって、5月5日が正式に「こどもの日」となりました。
この日付が選ばれたのは、すでに「端午の節句」として人々に馴染みがあったためです。
もともと多くの家庭で祝い事をしていた日を、祝日として制定することで、より広く国民に根付かせようとした意図が感じられます。
つまり、もとからあった文化と新しい価値観をうまく融合させて、今のこどもの日が形作られたというわけですね。
昔と今のこどもの日の違いとは
こどもの日って、実は時代によって祝い方や意味合いがだいぶ変わってきているんです。
「昔ながらのこどもの日」と「今どきのこどもの日」、それぞれの違いを見ていくと、日本の暮らしや価値観の変化も見えてきますよ。
昔は武士の儀式だった
こどもの日の前身である「端午の節句」は、もともと武士の世界の重要な儀式でした。
特に江戸時代になると、男の子が生まれた家では、家の門に家紋入りの旗を立てたり、刀や鎧兜を飾るようになりました。
これらは「一族の名を背負って立つ男子の誕生を祝う」意味がありました。
そして、将来の立身出世を願って、勇ましさや健康を象徴する品々で祝っていたんです。
まさに“家の誇り”として、男子を祝う伝統が根付いていたんですね。
今ほど「個人を大事にする祝日」ではなかったという点が、大きな違いです。
昭和の家庭の祝い方
昭和の時代になると、都市化が進み、核家族が増えていきます。
この頃のこどもの日は、家族単位で祝う行事へと変わっていきました。
鯉のぼりを庭やベランダに飾ったり、五月人形を室内に並べたりして、男の子の健やかな成長を祈りました。
また、柏餅やちまきを食べる習慣も広く定着しました。これらには「子孫繁栄」や「健康長寿」の意味が込められています。
この時代のこどもの日は、地域や家庭ごとに特色がありつつも、祝日として多くの人に定着していた印象です。
親子の思い出がたっぷり詰まった、温かい行事として記憶に残っている人も多いはずですよ。
今どきの家庭行事
令和の今、こどもの日の過ごし方も大きく変わっています。
一軒家ではなくマンション住まいの家庭が増えたことで、大きな鯉のぼりを飾る家は少なくなりました。
その代わり、室内用のミニ鯉のぼりやコンパクトな五月人形を飾る家庭が増えています。
また、InstagramやTikTokなどSNSの普及で、「映える」こどもの日を意識する傾向も出てきました。
こどもに手作りの兜をかぶせたり、柏餅の代わりにキャラクターケーキを用意したりと、スタイルは自由自在。
形は変われど、“子どもの成長を祝いたい”という想いは今も変わらず引き継がれていますよね。
保育園・学校での扱い
今では保育園や幼稚園、小学校などでも、こどもの日に関する行事が行われるのが一般的になっています。
園では、折り紙で鯉のぼりを作ったり、歌をうたったりして、楽しく学べるよう工夫されています。
小学校でも、こどもの日にちなんだ道徳の授業や家庭科の活動が行われることがあります。
こうした活動を通して、こどもたちは「自分が大切にされている存在」だということを実感できるんですよね。
そして、家庭だけでなく、地域や教育現場でも子どもの成長を祝う文化が定着してきたという点は、現代ならではの良さだと感じます。
世界の子どもの日と何が違う?
こどもの日は日本だけの文化…と思われがちですが、実は世界各国にも「子どもの日」があるんです。
でも、その意味や日付、祝われ方は国によってさまざま。
日本のこどもの日と世界の子どもの日を比べてみると、文化の違いや価値観がよく見えてきますよ。
国連の定めた子どもの日
まず、世界的に有名なのが「ユニバーサル・チルドレンズ・デー(Universal Children’s Day)」です。
これは国際連合(国連)が1954年に提唱したもので、毎年11月20日に世界中で「子どもの権利」について考える日とされています。
この日は、子どもたちの健全な成長や教育を支援するために制定されたもので、お祝いというよりは「啓発活動」が中心。
各国でイベントやセミナー、学校の取り組みなどが行われ、貧困や虐待、教育格差といった問題に注目が集まります。
つまり、日本の「家族で祝うこどもの日」とはちょっと方向性が違うんですよね。
日本との祝日文化の違い
日本のこどもの日は、祝日として家族が集まり、子どもの健やかな成長を“明るく・楽しく”祝う日として定着しています。
でも、世界の子どもの日は祝日として認識されていない国が多く、イベントや活動として静かに行われるケースが主流です。
また、「子どもが大切な存在である」という概念は共通していても、文化の中での“子どもの位置づけ”は国によって異なります。
例えば、ある国では“労働力”として子どもが扱われていたり、学校に行けない子が多い地域もあります。
そうした課題に目を向ける日として、世界の子どもの日は社会的な意味合いが強いわけです。
日本のように“家族で楽しむ日”という位置づけは、実は少数派なんですよね。
アジア諸国の事例
アジアの近隣国でも、こどもの日的な行事は存在しています。
たとえば韓国では、5月5日が「子供の日」として日本と同じく祝日になっています。
遊園地や動物園が無料になったり、イベントが行われたりするなど、日本と近いスタイルです。
中国では「六一儿童节(リウイーアールトンジエ/6月1日)」があり、学校での特別行事や公園イベントなどが行われることが多いです。
祝日ではないものの、子どもたちのために特別な時間が設けられます。
タイでは1月の第2土曜日が「子どもの日(Wan Dek)」で、こちらも軍の施設開放や遊園地の無料開放があり、大盛り上がり。
アジアでも、子どもを祝うという点では共通しているものの、日付や祝われ方には大きな違いがあります。
海外の祝い方まとめ
海外の子どもの日は、日本のように“鯉のぼりを飾る”“ちまきを食べる”といった伝統行事はあまり見られません。
代わりに、政府や自治体が主導する社会的なイベントや、学校主体の教育プログラムが中心です。
「子どもが大切な存在である」という認識はどの国にもありますが、表現の仕方や日付の由来は文化によってまったく異なるのです。
日本のように“古い行事が現代に受け継がれている”スタイルは、むしろユニークな存在といえるでしょう。
こうやって比較してみると、世界の中でも日本のこどもの日は、かなり独自性のある祝日だということがよく分かりますね。
家族で話したくなるこどもの日トリビア集
こどもの日の基本を押さえたら、ちょっとした雑学や豆知識も知っておきたいところ。
家族での会話や、子どもに説明するときに役立つトリビアを集めてみました!
鯉のぼりの意味
鯉のぼりには、「どんな困難にも打ち勝って、大きく立派に成長してほしい」という願いが込められています。
これは、中国の故事「登竜門」にちなんだもの。黄河をさかのぼった鯉が、激流の滝を登りきると龍になるという伝説です。
この鯉のように、子どもが元気でたくましく育ってほしいという思いが、鯉のぼりに託されているんですね。
また、鯉のぼりの色にも意味があります。一般的に、黒は父、赤は母、青や緑は子どもを表していると言われています。
「なんで鯉なの?」と聞かれたときは、こうした意味を語ってあげると、ぐっと深みが出ますよ〜。
柏餅とちまきの理由
こどもの日に食べるものといえば「柏餅」と「ちまき」ですよね。
柏餅は、関東地方を中心に食べられるお菓子で、「柏の葉」は新芽が出るまで古い葉が落ちないことから、“家系が途切れない”という縁起物とされています。
一方で、関西地方では「ちまき」が主流。もち米を笹の葉で包んだ細長い形は、もともと魔除けの意味を持っていたそうです。
どちらも「子孫繁栄」や「健やかな成長」を願う食べ物として、長く親しまれてきました。
地域によって違いがあるのも面白いところなので、実家や祖父母に聞いてみると新しい発見があるかもしれませんね。
五月人形や兜の由来
五月人形や兜を飾るのは、もともと「災いから子どもを守る」ためなんです。
特に鎧や兜は、武士の命を守る大切な道具。これを子どもに見立てた人形と一緒に飾ることで、「病気や事故から守ってくれるように」と願ったのが始まりです。
また、五月人形の中には有名な武将をモデルにしたものも多く、勇ましい姿に憧れる子どもたちの心を育てる役割もありました。
最近では、兜のみのコンパクトな飾りや、現代風にアレンジされた可愛い人形も増えていて、どんな家庭にも取り入れやすくなっていますよね。
飾る意味を知っておくと、ただの“イベント”じゃなくて、ぐっと気持ちのこもったものになりますよ〜。
本当は子ども全員の日?
よく「こどもの日は男の子のための日、女の子はひな祭りでしょ」と言われることもありますが、実はそれ、少し誤解なんです。
こどもの日は、祝日法によって「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかる日」として定められていて、男の子・女の子を問わずすべての子どもたちのための祝日なんです。
とはいえ、風習としては今も「鯉のぼり=男の子」というイメージが強く残っているので、混同されがちですね。
でも、近年ではジェンダーにとらわれず、男女ともに“こどもの成長を祝う日”として認識されるようになっています。
家族で過ごす中で、こうした話題を取り上げてみるのも、子どもの学びや気づきにつながっていきますよ。
まとめ
こどもの日は、ただのお祝いイベントではなく、日本人の暮らしや価値観の変化が色濃く映し出された行事なんですね。
古代中国から始まり、武家文化、戦後の法制度、そして現代の家族文化へと、時代を超えて受け継がれてきたこの日には、深い意味が込められています。
ぜひ、今年の5月5日は「なぜ祝うのか?」を家族みんなで語り合ってみてくださいね。