「こどもの日といえば柏餅じゃないの?」
そう思っていたのに、関西では“ちまき”を食べる家庭も多いんですよね。
そもそも、どうしてこどもの日に“ちまき”を食べるのでしょうか?
その理由や由来を知っている人は意外と少ないかもしれません。
この記事では、ちまきの起源から中国の故事、柏餅との違い、そして子どもにわかりやすく伝えるコツまで、丸ごと解説していきます!
「ちまきってなんで食べるの?」と子どもに聞かれたとき、スッと答えられるようになりますよ。
こどもの日にちまきを食べる理由をわかりやすく解説
「そもそも、こどもの日にちまきを食べるのって、どうしてなんだろう?」
そんな素朴な疑問から、まずはその由来や意味について、やさしく解説していきますね。
中国の故事が起源
実は、ちまきをこどもの日に食べる習慣って、日本独自のものじゃないんです。
起源をたどると、なんと中国までさかのぼります。
中国では古くから「端午の節句(たんごのせっく)」という行事があって、これが日本のこどもの日のルーツでもあるんですよ。
この端午の節句の際に食べられていたのが“ちまき”。
もともとは、もち米を笹の葉で包んだ保存食みたいなもので、それを川に流した…という伝承も残っています。
つまり、「ちまき」は、こどもの日=日本だけの風習ではなく、アジア全体で見ても長い歴史のある伝統食なんですよね。
こういう文化の流れを知ると、食べ物にもストーリーがあるって思えて、なんだか楽しくなりますよね。
屈原とちまきの関係
ちまきと深い関わりのある人物として「屈原(くつげん)」という詩人がいます。
中国・戦国時代の人で、民のことを真剣に考える正義感の強い人だったんですが、政治に裏切られ、絶望して川に身を投げてしまったと伝えられています。
その屈原の魂を慰めるために、村人たちが川にちまきを投げ込んだというエピソードがあるんです。
ただの食べ物じゃなくて、“思い”を込めた供物だったんですね。
だから、ちまきには「厄除け」や「供養」の意味合いもあるんです。
それが転じて、今のこどもの日に「健康に育ちますように」と願いを込めて食べるようになった、というわけなんですね。
こういう話、子どもにも話してあげると「へぇ〜」って興味持ってくれたりしますよ。
魔除けや厄払いの意味
ちまきって、実は「魔除け」の意味もあるんですよ。
もち米を笹の葉や真菰(まこも)で巻いて作るスタイルは、悪い気や災いを寄せ付けないという考えから来ています。
昔の人は、ちまきを食べることで「病気にならないように」「厄を払って健康でいられるように」って願いを込めていたんですね。
特にこどもの日は、元々「男の子の健康と成長を祝う日」だったので、その願いを込めた食べ物としてぴったりだったというわけです。
意味を知ると、ただ食べておいしいだけじゃなくて、なんか心があったかくなりますよね。
子どもの成長を願う風習
こどもの日って、そもそも子どもの健やかな成長を祝う日ですよね。
だから食べるものにも「意味」や「願い」が込められているのは自然なことなんです。
ちまきは、端午の節句に由来する食べ物で、「無病息災」「健やかな成長」「厄除け」など、いろんな祈りが込められているんです。
今は見た目や味で選ばれがちだけど、実は昔からずーっと大事にされてきた伝統食なんですよね。
子どもに「なんでちまき食べるの?」って聞かれたとき、この話をしてあげたら、きっと心に残ると思いますよ。
柏餅との違い
ここで「え、こどもの日って柏餅じゃないの?」と思った方も多いと思います。
実は、関東を中心に「柏餅」、関西を中心に「ちまき」という風に、地域によって風習が違うんです。
柏餅は、柏の葉が「新芽が出るまで葉が落ちない=家系が絶えない」という縁起の良さから選ばれたもの。
一方のちまきは、さっき話した通り、厄除けや供養の意味が強いです。
どちらも「子どもが健康に育ちますように」という願いが込められていますが、由来や食文化に違いがあるんですね。
地域によっては両方食べるところもあるので、自分の家の文化を知っておくのも大事ですね。
関西でちまき、関東で柏餅になる理由とは?
「でも、こどもの日といえば“柏餅”じゃないの?」と思った方も多いはず。
実はこの違い、地域ごとの文化が大きく関係しているんです。
地域ごとの文化背景
こどもの日の食べ物って、実は地域によってけっこう違うんです。
関東では「柏餅」が主流ですが、関西では「ちまき」を食べる家庭が多いんですよ。
この違いには、昔からの文化や風習が深く関わっているんですね。
関東では江戸時代に柏の木が多く自生していて、「柏餅」という文化が自然と広まりました。
一方、関西では中国からの文化の影響が強く、端午の節句にちまきを食べる風習がそのまま根づいたんです。
だから「なぜ関西はちまき?」「え、こどもの日は柏餅でしょ?」っていう感覚の違いがあるんですね。
こういう文化の違いを知っておくと、旅先とかでも「へぇ~!」ってなったりしますよ。
関西と関東の食文化の違い
そもそも、関西と関東って料理の味つけや食材の使い方も違いますよね。
関東は濃いめの味、関西は出汁を大事にした薄味文化。
こうした食文化の違いが、行事食にも影響しているんです。
柏餅はあんこを包んだ甘味で、関東の行事食として馴染みが深い。
一方、関西のちまきは、甘くてつるんとしたもち米を真菰(まこも)の葉で巻いた、やや和菓子寄りのイメージ。
ちなみに関西のちまきって、見た目は中華ちまきとは全然違ってて、甘~いタイプも多いです。
「ちまき=おかず系」と思ってると、関西のちまき見てビックリしますよ。
関西ちまきの特徴とは?
関西のちまきには、独特な魅力があります。
まず形。とんがりコーンみたいに先が細くなっていて、葉でしっかり巻かれてます。
そして味。多くは“甘くてやわらかい”もち米を蒸してあって、まるで和菓子のような口あたり。
中華ちまきのように具材が入ってるわけではなく、素材のやさしさを活かした上品な味なんです。
「これがちまきなの!?」って初めて食べた人は、ちょっとびっくりするかも。
ちなみに笹の香りがほんのり移ってて、子どもにも食べやすいので、こどもの日のデザートにもピッタリなんですよね。
柏餅が広まった背景
じゃあ、どうして関東では柏餅がメジャーになったんでしょうか?
江戸時代、柏の葉って関東に多く自生していたんです。
しかも柏の木は「新芽が出るまで古い葉が落ちない」という性質があって、これが「家系が途絶えない」「代々続く家族の繁栄」として、縁起物とされました。
そのため、「子孫繁栄」の願いを込めた柏餅が、こどもの日の食べ物として大流行したんですね。
江戸っ子たちの間で「男の子の健やかな成長を祝う食べ物」として根付いたわけです。
だから現代でも、こどもの日=柏餅っていうイメージが定着してるんですよ。
こどもの日にちまきを食べる風習はいつから?
ちまきの由来や地域差がわかったところで、次に気になるのは「この風習っていつからあるの?」というところ。
歴史をひも解きながら、ちまきが行事食として根づいた背景を見ていきましょう。
日本に伝わった時期
ちまきの風習が日本に入ってきたのは、奈良時代〜平安時代ごろといわれています。
もともと中国から伝わった端午の節句の文化が、日本の宮中行事として取り入れられたのが始まりなんですね。
当時の日本では、中国の文化や制度を積極的に取り入れていたので、ちまきもそのひとつだったわけです。
ちなみに当時のちまきは今のようにお菓子感覚じゃなく、儀式や供物としての意味が強かったと考えられています。
現代とはだいぶ意味合いが違っていて、歴史って面白いな〜って思いますよね。
江戸時代の行事食
江戸時代に入ると、端午の節句は「男の子の成長を祝う日」として庶民の間にも広まっていきました。
このころには、ちまきが節句の定番行事食になっていたんです。
また、武家社会では「兜」や「鯉のぼり」が飾られるようになり、「男の子の強さ・たくましさ」を象徴するイベントとして定着していきました。
その一方で、食べ物にも「健康に育ちますように」「厄を払って元気に成長してほしい」という願いが込められていたんですね。
つまり、ちまきはただの伝統ではなく、“親の願いが詰まった食べ物”でもあったということです。
現代でも続く理由
現代のこどもの日は、レジャーに出かけたり、プレゼントを用意したりと、イベント化が進んでいますよね。
でも、ちまきや柏餅のような伝統的な行事食も、変わらず大切にされているのが面白いところ。
これはやっぱり、「家族で一緒に過ごす日」だからこそ、“伝統を感じられる食べ物”が求められてるのかなと思います。
スーパーや和菓子屋さんに並ぶちまきを見て、「あ、もうすぐこどもの日だな」って思う人も多いはず。
昔からの行事が、今も私たちの暮らしにちゃんと溶け込んでるのって、なんだかホッとしますよね。
学校や家庭のイベントとして定着
今では、保育園や小学校などでも、こどもの日が近づくと「ちまきづくり」や「柏餅体験」などのイベントをすることもありますよね。
行事食を通じて、子どもたちが日本の文化や歴史に触れる機会になっているのは、本当に素晴らしいことです。
また、家庭でも「ちまきを一緒に作ってみよう!」という流れが広がってきていて、親子のふれあいにもなっています。
SNSなんかでも、手作りちまきをアップしてる人、結構見かけますよね。
“伝統=堅苦しい”じゃなくて、“楽しみながら伝える”というスタイルが増えてるのは、すごくいい流れだなと思います。
子どもに「なぜちまきを食べるの?」と聞かれたらどう答える?
意味や歴史を知ると、大人としては「子どもにもちゃんと伝えてあげたいな」って思いますよね。
この章では、子ども向けにやさしく説明するコツをご紹介します!
簡単に伝えるポイント
子どもに「なんでちまき食べるの?」と聞かれたとき、どう答えるか迷っちゃいますよね。
そんなときは、難しい歴史よりも「元気に育ってほしいから、って願いがこもってる食べ物だよ」ってシンプルに伝えるのがコツです。
例えばこんな感じで話してみるのもおすすめです。
「昔から、ちまきには“病気にならないように”とか“悪いものが近づかないように”っていう意味があるんだって。だからこどもの日に食べると元気になれるんだよ~!」
こうやって話すと、子どもも「そっかー!」って納得してくれやすいです。
まずは“願いを込めて食べるもの”ってイメージを伝えることが大事なんですよね。
屈原の話を子ども向けにするには
ちまきの由来に出てくる「屈原」の話も、できれば伝えたいところ。
ただし、大人向けのままだとちょっと難しいので、子ども向けにアレンジするのがポイントです。
例えばこんなふうに言い換えるといいかもしれません。
むかしむかし、やさしいおじさんがいてね、みんなのことをすごく大事にしてたんだ。
でもその人がすごく悲しいことがあって、川に飛びこんじゃったの。
それを見た人たちが“魚に食べられないように”って、おにぎりみたいなものを川に投げたんだって。
それが“ちまき”の始まりなんだよ~!
こうすると、小さな子でもイメージしやすくなります。
物語として伝えることで、記憶にも残りやすいんですよね。
伝統文化を教えるチャンス
「ちまきってなんで食べるの?」っていう質問って、実は絶好の“教育チャンス”でもあるんですよね。
こどもの日というタイミングで、行事の意味や日本と中国の文化、昔の人の考え方を、さりげなく伝えられる機会になります。
例えば「今はイベントって感じだけど、昔の人たちはこういうふうに願いを込めてたんだよ」なんて話すと、食べ物ひとつにも“意味があるんだ”って気づいてくれるかもしれません。
伝統行事って、お祭りだけじゃなくて“想いを伝える文化”なんだなって思うと、大人も勉強になりますよね。
子どもと一緒に、親も学び直せるのがいいところなんですよ。
親子で一緒に作って学ぼう
ちまきって、見た目も楽しいし、作る工程もワクワクしますよね。
だから、「話す」だけじゃなくて「一緒に作る」ことで、子どもにもっと深く印象づけられます。
実際にもち米を包んで、蒸して、笹の香りを感じながら食べる。
そんな体験を通して、「あ、これがこどもの日のちまきなんだ!」って、心に残る思い出になります。
最近は、簡単に作れるちまきキットなんかも売ってるので、親子でチャレンジしやすいです。
「一緒に作ったね」「なんで食べるか知ってるよね?」って会話ができるのって、すごく素敵な時間だと思います。
まとめ
こどもの日にちまきを食べる理由は、ただの風習じゃなくて、深い意味や歴史があったんですね。
中国の故事から始まり、日本の風習として根づいた“ちまき文化”。
そして、それを次の世代に伝えていくのも、私たち大人の役目かもしれません。
「健康に育ってほしい」「元気にすくすく大きくなってほしい」
そんな願いを、ちまきと一緒に子どもに伝えてみてください。
こどもの日が、もっと思い出深い1日になりますように。




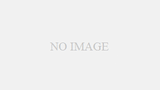
コメント