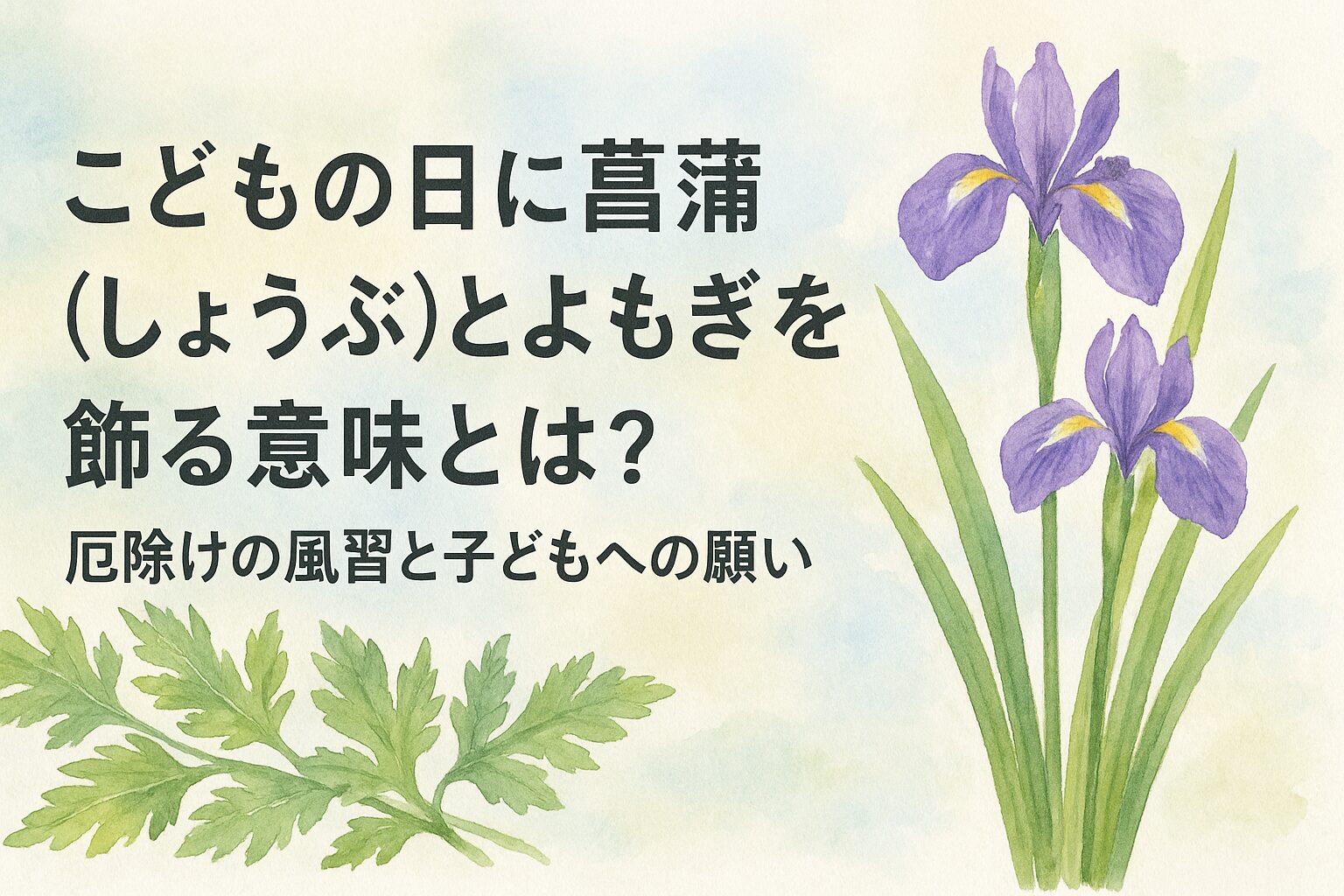5月5日の「こどもの日」といえば、こいのぼりや柏餅が定番ですが、実は“菖蒲”や“よもぎ”も大切な役割を担っているのをご存知ですか?
昔ながらの行事には、子どもたちの健康や幸せを願う深い意味が込められています。
- こどもの日に菖蒲とよもぎを飾る理由
- それぞれの植物がもつ厄除けの力
- 端午の節句が男の子の節句となった背景
- 家庭でできる菖蒲湯やよもぎ餅の楽しみ方
- 子どもと一緒に伝統文化を感じるアイデア
この記事を通じて、忙しい日常の中でも気軽に取り入れられる「行事の知恵」と「親子のふれあい方」を見つけてみてくださいね。
こどもの日に菖蒲とよもぎを飾る意味とは?
こどもの日といえば、こいのぼりや柏餅が有名ですが、実は菖蒲やよもぎを使う風習にも大切な意味があるんです。
古代から受け継がれてきたこの習わしには、ただの飾りではない「厄除け」の力が込められているんですよ。
菖蒲とよもぎが持つ厄除けの力
こどもの日に飾られる菖蒲やよもぎには、古くから「邪気を払う力がある」と信じられてきました。
特に菖蒲は、葉の形が刀のように見えることから、悪いものを切り払う象徴とされてきたんです。
また、その強い香りには虫を遠ざけたり、心を落ち着ける効果もあると考えられており、古代中国では薬草としても重宝されていました。
よもぎもまた同様に、香りによって悪い気を追い払うとされ、端午の節句では家の軒先に吊るしたり、お餅に混ぜて食べたりして健康を祈願していたそうですよ。
こうした植物の力にあやかって、大切な子どもたちを病気や災いから守ろうという思いが、こどもの日には込められているんですね。
中国由来の風習と日本での受け継がれ方
こどもの日に菖蒲やよもぎを飾る風習は、実は中国から伝わってきたものなんです。
古代中国では、旧暦5月5日は季節の変わり目で病気が流行りやすいとされ、「端午節(たんごせつ)」という厄除けの行事が行われていました。
そのときに使われていたのが、香りの強い菖蒲やよもぎ。
邪気を追い払う効果があるとされ、家の入口に吊るしたり、入浴剤のように使ったりして、健康を守ろうとしていたそうです。
この習わしが日本に伝わったのは奈良時代ごろ。
貴族の間で菖蒲を浮かべた「菖蒲湯」に入る風習が広まり、そこから庶民の間にも伝わっていきました。
やがて、端午の節句が武士の時代に入ると、菖蒲の音が「勝負」と通じることから、男の子の成長や出世を願う日として定着していったのです。
つまり、菖蒲とよもぎには単なる香りや植物以上の「伝統と祈り」が詰まっているというわけですね。
厄除けの風習と子どもへの願いとは?
菖蒲とよもぎの力が注目される背景には、日本ならではの文化的な意味合いもあるんです。
特に端午の節句が「男の子の健やかな成長を願う日」として定着したことは、古くから続く祈りのかたちともいえます。
端午の節句が「男の子の節句」になった理由
端午の節句はもともと男女問わず健康を願う行事でしたが、日本では鎌倉時代以降、次第に「男の子の節句」としての色が濃くなっていきました。
そのきっかけとなったのが、武士社会の価値観です。
武士たちは「勝負」や「武運」をとても大切にしており、同じ読みの「菖蒲(しょうぶ)」に縁起を感じるようになったんですね。
さらに、菖蒲の葉が刀のように見えることもあり、武士にとっては「強さの象徴」として特別な意味を持つようになりました。
このような流れの中で、5月5日は次第に「男子の成長や強さ、出世を願う日」として定着し、鎧や兜、武者人形を飾る習慣も生まれていったんです。
つまり、こどもの日に菖蒲やよもぎを使うことは、ただの季節行事ではなく、子どもの未来を思う深い願いが込められているということなんですね。
続いては、そんな行事に込められた「健康祈願」や「無病息災」の意味について詳しく見ていきましょう。
健康祈願と無病息災の願いを込めて
こどもの日に菖蒲やよもぎを使う風習には、「子どもが健やかに育ちますように」という願いが込められています。
古くから植物には不思議な力があると信じられていて、特に香りの強い植物は「邪気を払う」「病気を遠ざける」と考えられてきました。
そのため、季節の変わり目で体調を崩しやすい5月初旬に、菖蒲やよもぎを使って健康を祈る風習が広まったんですね。
また、こどもの日は「子どもの人格を重んじ、子どもの幸福をはかる日」として、戦後に国民の祝日として制定されました。
昔からの伝統行事である端午の節句と、現代の「こどもの日」が重なったことで、今では「子どもたちの健康や幸せを願う日」として認識されています。
つまり、菖蒲やよもぎを飾るのは昔ながらの厄除けの意味だけでなく、今の時代にも通じる「思いやり」や「願い」が詰まっているんですよ。
現代でもできる!菖蒲とよもぎの取り入れ方
昔ながらの伝統行事も、少し工夫をすれば今の暮らしにも無理なく取り入れられるんです。
菖蒲湯やよもぎ餅など、子どもと一緒に楽しめる簡単な方法を知って、こどもの日をもっと身近な行事にしてみませんか?
家庭で楽しめる菖蒲湯とよもぎ餅の作り方
こどもの日をもっと身近に楽しむなら、やっぱり菖蒲湯やよもぎ餅をおうちで取り入れてみるのがおすすめです。
菖蒲湯
これは菖蒲の葉をお風呂に浮かべるだけでOK。
香りが立って気分もリラックスできるし、湯冷めしにくいという嬉しい効果もありますよ。
葉っぱはスーパーの和菓子売り場や花屋さん、道の駅などで手に入ることもあります。
よもぎ餅
これは春先によもぎを摘んで冷凍しておいたものを使うと便利です。
米粉や白玉粉と混ぜてこね、蒸し器で蒸したあとにあんこを包めば完成。
市販のよもぎ粉や冷凍よもぎを使えばもっと簡単に作れます。
どちらも子どもと一緒に作ったり体験したりできるので、「伝統行事に触れるきっかけ」にぴったりなんです。
子どもと一緒に伝統文化を楽しむアイデア
こどもの日は、ただ行事を“こなす”だけじゃなく、子どもと一緒に意味を感じながら楽しむのがいちばんです。
たとえば、菖蒲湯を用意するときには「この葉っぱ、昔の人は魔除けに使ってたんだよ」と話してあげるだけで、子どもにとってぐっと興味が湧きます。
よもぎ餅を作るときも、材料に触れながら「いい香りだね」「春の草なんだって」と五感を使って楽しむのがおすすめです。
また、菖蒲の葉を使ってかぶとを折ったり、よもぎの絵本を一緒に読んだりするのも、文化を知るきっかけになりますよ。
SNSで見かける「菖蒲風呂におもちゃを浮かべてバスタイムを演出」なんてアイデアも、子どもが大喜びしそうですよね。
こうした工夫を通じて、行事が「学び」と「楽しい思い出」の両方になると、伝統も自然と心に残っていきます。
まとめ
今回の記事ではこんなことを書きました。以下に要点をまとめます。
- こどもの日に菖蒲とよもぎを飾るのは、邪気を払うための伝統的な風習である
- 菖蒲は刀に似た形と香りから、悪いものを断ち切る力があると信じられてきた
- よもぎも香りによって災厄を避ける植物として、中国から伝わった歴史がある
- 武家文化と結びついて端午の節句が男の子の節句とされ、健康と出世を願う行事へ
- 現代でも、菖蒲湯やよもぎ餅を通して親子で伝統文化に触れることができる
この記事を読むことで、「なぜこどもの日に菖蒲やよもぎを使うのか?」という疑問がスッキリ解決できたと思います。
そして、伝統行事は難しいものではなく、ちょっとした工夫で今の生活にも楽しく取り入れられるということが伝わったのではないでしょうか。
ぜひ今年のこどもの日は、おうちでも菖蒲やよもぎを使って、子どもたちと楽しく健康を願うひとときを過ごしてみてくださいね。