「兜ってどちらの親が買うのが正解なの?」そんな疑問を感じたこと、ありませんか?
この記事では、「兜 どちらの親が 買う」というキーワードをもとに、昔ながらの風習から、最近のリアルな事情、トラブルを防ぐための対処法まで、わかりやすくまとめました。
誰が買うべきかで悩んでいるママやパパが、この記事を読むことでモヤモヤがスッキリするはず。
また、兜の選び方やおすすめブランドも紹介しているので、「実際にどんな兜を選べばいいのか?」というところまでお手伝いしますよ。
読み終わったあとには、両家の関係もスムーズに、お子さまの初節句がとっても素敵な思い出になる未来が待っています。
どうぞ最後までチェックしていってくださいね。
兜はどちらの親が買うのが正解なの?
「兜はどちらの親が買うのが正解なの?」という疑問、多くのご家庭で悩まれるポイントですよね。
特に初めての男の子が誕生したご家庭では、節句の準備をどう進めるか、両家の親との関係にも関わってくる大切なテーマです。
それでは、ここから詳しく解説していきますね。
昔の風習では母方の実家が買うとされていた
昔からの日本の慣習では、初節句で飾る兜や五月人形は「母方の実家が贈る」とされてきました。
これは、嫁ぎ先への感謝や、男の子の健やかな成長を願う気持ちを込めて母方の親が用意する、という意味があるんですよ。
今でも一部の地域ではその風習が強く残っていて、祖父母が張り切って立派な兜を選ぶケースもよくあります。
でも、地域や家庭によって考え方はさまざまなので、必ずしも「母方が買うべき」と思い込む必要はありません。
大切なのは、子どものためを思って用意してくれる気持ちですから、誰が買うかにこだわりすぎないのもポイントですね。
最近では両家折半や両親が購入も増加中
最近は、「どちらの親が買うか」よりも、「両親で買った方が気がラク」というご家庭が増えています。
共働き世代のママパパは、自分たちで選びたい気持ちも強く、「好みに合うデザインで飾りたい」という声もよく聞きます。
また、両家の経済状況が異なる場合なども、「折半にしよう」や「自分たちで全部出すよ」と柔軟に対応するパターンが主流になっています。
最近ではネットで簡単に購入できるので、お互いの実家に負担をかけたくないという思いもあるのかもしれませんね。
親としては「どちらが出したかより、孫の喜ぶ顔が見たい!」という気持ちが一番大きいのではないでしょうか。
家庭によって事情はさまざま
兜を誰が買うかという問題、実は一概には言えないんですよね。
例えば、片親家庭や、実家と疎遠な場合、あるいは遠方でそもそも関与が難しいこともあります。
また、「そういう風習にはこだわらない」というご家庭も多く、自由な価値観が広がっています。
とくに都市部では「飾るスペースがない」問題もあるので、小さいサイズやケース入りの兜を両親が選ぶというパターンも人気です。
つまり、どちらの親が買うかよりも、その家庭ごとのスタイルに合わせた方法が一番なんですよね
親族間トラブルを防ぐには事前の話し合いが重要
このテーマで一番注意したいのが、「知らぬ間にトラブルになってしまう」こと!
「母方が買うのが常識でしょ?」と考えるおばあちゃんと、「そんなの聞いてない…」という嫁側との意見の違いが火種になることもあるんです。
大切なのは、事前に両家で話し合って、気持ちよくお祝いできる環境を整えること。
「うちはこう考えてるよ」「お祝いしたい気持ちは同じだよ」と一言伝えるだけでも、スムーズに進むことが多いですよ。
贈り主によって選び方や予算も変わる
兜って、種類も価格帯もすっごく幅広いんです!
数千円のミニチュアタイプから、何十万円もする伝統工芸の本格派まであって、贈り主によっても選ぶ基準が変わります。
祖父母が贈る場合は、「一生モノを贈りたい」と思って奮発する方も多いですし、両親が買う場合は「収納しやすさ重視」で選ぶ傾向もあります。
予算の感覚も世代によってズレがあるので、事前に希望や予算感を共有しておくと、失礼にならずに済みますよ♪
見た目やサイズだけじゃなく、意味や素材にもこだわることで、より満足度の高い兜選びができます。
「誰が買うか」より「どう祝うか」を大切に
結局のところ、一番大事なのは「誰が買ったか」じゃなくて、「家族で楽しくお祝いできたか」なんですよね♪
初節句は、男の子の成長を願う特別なイベント。
豪華な兜がなくても、写真を撮ったり、ささやかにごちそうを囲んだりするだけでも、素敵な思い出になります。
兜にこだわりすぎず、家族全員が笑顔で過ごせる一日になるように工夫することが大切です。
「お祝いのカタチ」は、もっと自由でOK!これからの時代は、柔軟さも大事ですよね。
SNSの声や実際の体験談もチェックしよう
最近ではX(旧Twitter)やInstagram、ママ向け掲示板などで、リアルな体験談がたくさんシェアされています。
「うちは両親が買って、義実家は料理担当にしたよ」とか、「お返しにフォトブックをプレゼントしたら喜ばれた!」など、参考になるアイデアもいっぱい!
同じ悩みを持つママたちの本音は、本当に心強いですし、トラブルを防ぐヒントにもなります。
自分たちのケースと照らし合わせながら、取り入れられる部分を柔軟に考えてみましょう。
兜はどちらの親が買う場合の注意点
兜はどちらの親が買う場合の注意点でありがちなトラブルや気遣いポイントを押さえておくと安心です!
ここでは、事前の話し合いやお返しのマナーなど、リアルな注意点を紹介していきますね。
事前に両家と話し合うタイミングとは
初節句の準備は意外とバタバタしやすいから、兜を誰が買うかっていう話はできるだけ早めに相談するのがコツなんです。
おすすめのタイミングは、男の子の誕生後、内祝いがひと段落した頃。お宮参りが終わったあたりで話題にすると自然ですよ。
例えば「初節句どうしようかって話してて…」と雑談の流れで切り出せば、プレッシャーを与えずに相談できます。
あとで「聞いてなかった!」なんてことにならないよう、LINEでもOKなので、両家に軽く相談しておくといいですよ。
LINEグループを作って、みんなで「こんなの可愛いね〜」って画像送りあうのもいいかもしれませんね。
トラブルになりやすいパターンとその回避法
ありがちなのが、「母方が買うのが当然」と思い込んでた義母が、先に用意してしまってたパターン…!
一方で、「うちはそんな風習知らないし、今どき自分たちで買うよ〜」って考えのママパパも多いんですよね。
このギャップがあると、どうしてもモヤモヤが生まれちゃういます。
対策としては、「誰が買うか」だけでなく「どういう形でお祝いしたいか」を早めに共有することが大事!
「一緒に選びに行こう」と誘ったり、「気持ちだけでありがたいよ」と伝えるだけで、誤解を避けられますよ。
贈られた場合のお返しマナー
祖父母から兜を贈られたとき、「お返しって必要?」って悩む方、多いですよね。
基本的に、初節句のお祝いに対して明確なお返しは不要とされてるんですけど、感謝の気持ちはきちんと伝えたいところ!
最近多いのは、「孫の写真入りギフト」や「節句当日の写真をアルバムにまとめて贈る」などのカジュアルなお礼のようです。
食事会を開いたり、手料理をごちそうするのもすごく喜ばれます。
フォトフレームに節句の写真を入れてプレゼントしてもいいかもしれませんね。
感謝の気持ちを伝える方法やアイデア
感謝の気持ちって、ちゃんと言葉にするのってちょっと照れますよね。
でも、やっぱり「ありがとう」は言われると嬉しいし、ちゃんと伝えてよかったって思います!
例えば、LINEで写真付きのメッセージを送ったり、お手紙を同封したりすると、グッと心に響きますよ。
あと、節句当日に一緒に写真を撮って、みんなでお祝いする時間をつくるのも、最高のお礼になります!
思い出に残る形でお礼を伝えられると、贈ってくれた側もすごく嬉しいですし、家族の絆も深まるんですよね。
兜はどちらの親が買うので迷ったときの対処法
「結局どちらの親が買えばいいの?」「なんとなく決まらない…」そんなときこそ冷静に対処していきましょう!
この章では、実際に迷ったときのスマートな解決法や、関係を悪くしない工夫を紹介していきます。
費用を分担するケースとそのメリット
最近とっても増えてるのが、両家で費用を折半するスタイルです!
たとえば「5万円ずつ出し合って10万円の兜を買う」とか、「兜は母方、他の飾りは父方が担当」といったパターンもアリです。
この方法なら、どちらの親も“関わった感”があるし、不公平感も少ないんです。
費用分担のメリットは、節約にもなるし、気持ちよくお祝いできる空気が作れること。柔軟な選択肢としておすすめです!
両親が購入する場合の進め方
「もうめんどくさいから自分たちで買っちゃおう!」というご夫婦も、実はたくさんいるんです。
このスタイルの良さは、「自分たちの好きなデザインを選べる」「価格も調整できる」「気を使わなくて済む」といった自由さ!
ただし、購入前に「○○円くらいで買おうと思ってる」と一言両家に伝えておくのがおすすめ。
そうすれば、「知らなかった!買おうと思ってたのに…」と気まずくなるのを防げますよ。
自分たちで用意して、当日は祖父母を招待して一緒にお祝いする…そんな“ハイブリッド型”も最近人気ですよ。
祖父母と良好な関係を保つコツ
どんな形を選んでも、やっぱり一番大切なのは「家族関係を良好に保つこと」ですよね。
たとえば、「お義母さんのアドバイスを参考にしたよ!」「一緒に選びたかった〜!」と、ちょっとした感謝の言葉や気遣いが効きます。
たとえ相手が買わなくても、「お祝いの気持ちは嬉しかったよ」と伝えるだけで印象がグッと良くなるんですよね。
お互いの価値観に配慮しつつ、思いやりのある言葉を選ぶと、ほんとに関係がスムーズにいきます。
兜の選び方と人気ブランド紹介
兜選びって、種類が多くて迷っちゃいますよね。
ここでは、コンパクトサイズや人気の素材、そして注目のブランドなど、選ぶときのポイントを分かりやすく紹介していきますね。
飾りやすいコンパクトタイプが人気
最近の主流はなんといっても、「コンパクト兜」!
昔ながらの立派な段飾りも素敵だけど、集合住宅やマンション住まいだと置き場所に困ることもありますよね。
その点、ケース入りや折りたたみ式のコンパクトタイプは、飾るのも片づけるのも楽ちん♪
しかもおしゃれなデザインが多くて、インテリアとしても楽しめちゃうんです!
名入れ・木製などこだわりポイント
「せっかく贈るなら、特別感があるものがいい!」って思いますよね。
そこで人気なのが、名入れプレート付き**や**木製・漆塗りの職人手作りシリーズ。
とくに最近は、ウォールナットやヒノキなど自然素材の温もりを感じられる兜がママパパから支持されてるんです!
ナチュラルテイストで写真映えもバッチリ♪しかも長く大切に飾れるって、嬉しいですよね。
選ぶときは「飾りやすさ+特別感」を意識すると、プレゼントにも自宅用にもぴったりですよ。
価格帯と選び方のポイント
兜の価格帯は、本当にピンキリ!だいたい1万円〜30万円超まであります。
コンパクトタイプなら、1万〜3万円台でもおしゃれなものがたくさん。
本格派の甲冑風デザインだと、10万円以上が目安。木製の手作りモデルは職人技の分、少しお高めになる傾向があります。
選ぶときのポイントは、「飾るスペース」「収納のしやすさ」「お祝いの主旨」に合わせて無理のない範囲で選ぶこと!
兜に関する基本情報とプロフィール
兜ってなんで飾るの?どんな意味があるの?
初節句にまつわる基本情報や豆知識をまとめて紹介していきますね。
兜の意味や由来
兜は、古くから「守り」の象徴とされていて、災いや病から子どもを守ってくれるお守り的存在なんです!
戦国時代、武将たちが頭部を守るためにかぶっていた兜が起源となっていて、「強く育ってほしい」「健やかに生き抜いてほしい」という願いが込められています。
現代では戦いというより、「困難にも負けずに立派に成長してね!」という意味で飾られることが多いですね。
兜=かっこいい!というイメージもあり、男の子の節句飾りとして定番アイテムになってますね。
五月人形と兜の違い
「五月人形と兜ってなにが違うの?」って思ったことありませんか?
実は、五月人形は「兜を含む一式のセット」を指すんです。中には鎧・刀・馬などがそろっているものも。
一方で、兜単体は「飾りやすさ」「価格の手軽さ」から、最近人気が高まっているんですよ!
豪華なセットにするか、シンプルな兜だけにするかは、家庭の事情やスペースに合わせて選んでOKですよ。
選び方に決まりはないので、「自分たちが気に入ったもの」を選ぶのが一番です。
初節句のタイミングと祝う意味
初節句とは、赤ちゃんが生まれて初めて迎える端午の節句(5月5日)のこと!
この日は「子どもが無事に成長してくれてありがとう」「これからも元気でいてね」という願いを込めてお祝いします。
食事会を開いたり、ちまきや柏餅を食べたりするのが伝統的なスタイルです。
最近は、おうちで手作りの飾り付けをして、フォトブースを作ったり、オリジナルフォトブックを作ったりと、記念に残す工夫をする人も多いんです。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 昔の風習 | 兜は母方の実家が用意するのが一般的とされていた |
| 現代の傾向 | 両親が自ら購入、または両家で折半するスタイルが増加 |
| トラブル防止法 | 事前に両家へ相談し、希望や予算感を共有することが大切 |
| お返しの工夫 | フォトブックや食事会などで感謝を形にするのが◎ |
| 人気の兜タイプ | コンパクトで飾りやすいデザインがトレンドに |
| 初節句の意味 | 子どもの健やかな成長を願い、家族で祝う特別な日 |
兜をどちらの親が買うか問題は、決して正解が一つじゃないんですよね。
家庭ごとの事情や価値観に合わせて、柔軟に対応していくことが一番大切!
大事なのは「誰が買ったか」ではなく、「どう祝って、どんな思い出を残せたか」。
家族みんなが笑顔になれる初節句になりますように。

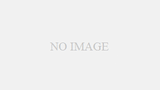
コメント